あなたとは誰か? 何故ここに居るのか?
この世界とは何か?
「写像」はこの世界を一言で表現した言葉です。このサイトには「写像」というタイトルの一遍の小説を掲載しています。世界の姿、人間としての理想的な生き方を、SF的なストーリーの中に描いてみました。登場人物達の生き様を通して、真の世界の姿を感受して頂けたら幸いです。
健康へのいざない・・・・これを実現できれば、健康・長寿は約束される
| 健康になる秘訣 7箇条 | ||
| 1 | 自然との調和 | 人間は自然と調和することで、心身を胎児の無垢な状態に戻すことができる。それは病を知らない完全な状態だ。 |
| 2 | 自己治癒力 | 人間は本来自分の中に、あらゆる病に対して、自らを治癒する仕組みを持っている。そのことを知ることが大切だ。 |
| 3 | 意識の作用 | 自分は常に健康で、幸福であると意識していること。病は自分からの警告である。回復して来ているという意識が大切だ。 |
| 4 | 愛すること | 対象を定めず、あらゆるものを愛すること。意識的に愛することが、自己、そして他者の心身の健康を招来する。 |
| 5 | 極端を避ける | 極端を避け、中なる道を進むことだ。食事、生活リズム、思い、欲望、何れも極端は破局に繋がる。中なる道が最良の道。 |
| 6 | 感謝すること | 自分が生かされていることに、常に感謝していること。あらゆる存在、事象に対し、常に感謝の気持ちを抱くこと。 |
| 7 | 自己を空しく | 可能な限り、自己を捨て、人のために生きること。この生き方が出来ると、健康以外の状態にはならない。 |
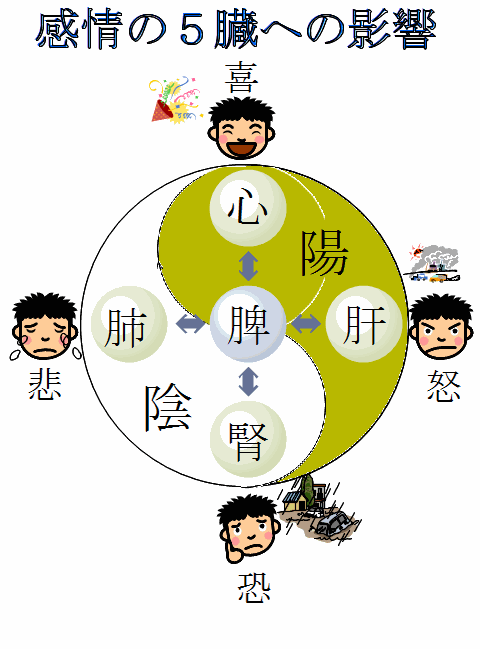
|
| 五臓のはたたきと五行との関係・・・・これを知り、調和をはかることで、あらゆる病変を退けることが出来る |
| 五 行 (五臓の働き・五臓への影響) |
| 五行(ごぎょう) | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | 五行の特性とその意味 |
| 五臓(ごぞう) | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | 心身の各部の働きを司る5つの主要臓器 |
| 五腑(ごふ) | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 | 心身の活動に作用する5つの主要腑 |
| 五根(ごこん) | 目 | 舌 | 唇(口) | 鼻 | 耳 | 五臓の病変が現れる部位 |
| 五指(ごし) | 薬指 | 中指 | 人差指 | 親指 | 小指 | 五臓に繋がり、五臓の機能に影響する指 |
| 五主(ごしゅ) | 筋・脈・腱 | 血脈 | 肌肉 | 皮膚 | 骨 | 五臓から栄養を補給する部位 |
| 五支(ごし) | 爪 | 毛 (面色) |
乳(唇) | 息 | 髪 | 五臓への栄養が悪いと異常をきたす部位 |
| 五気(ごき) | 風 | 熱 | 湿 | 燥 | 寒 | 五臓を傷つける気象条件 |
| 五季(ごき) | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 | 五臓が活発になりやすい季節 |
| 五方(ごほう) | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 | 五臓に適合する方位 |
| 五色(ごしき) | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 | 五臓の持つ特有色。顔色で病変を検知できる |
| 五香(ごこう) | 脂 | 焦 | 香 | 腥 (生臭い) |
腐 | 五臓の不調時に発する体臭・口臭 |
| 五味(ごみ) | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | しおからい | 五臓の要求する味。過度な味は害になる |
| 五傷(ごしょう) | 筋 | 気 | 肉 | 皮毛 | 血 | 五味によって傷つきやすい部位 |
| 五宣(ごせん) | 苦 | 甘 | 辛 | 塩 | 酸 | 五臓が弱っているときに、体調をただす味 |
| 五情(ごじょう) | 喜 | 楽 | 怨 | 怒 | 哀 | 五臓は感情の発生源 |
| 五志(ごし) | 怒 | 喜・笑 | 思・慮(考) | 悲・憂 | 恐・驚 | 五臓の担当する精神活動 |
| 五液(ごえき) | 泣 | 汗 | 涎 (よだれ) |
はなじる | 唾 | 五臓の担当する身体から出る体液 |
| 五役(ごやく) | 色 | 臭 | 味 | 声 | 液 | 五臓の担当する感覚・役割 |
| 五声(ごせい) | 呼・叫 | 言 | 歌 | 哭 | 呻 | 五臓が病んだときに発しやすくなる声の特徴 |
| 五穀(ごこく) | 麦 | 黍 (きび) |
粟 | 稲 | 豆 | 五臓の栄養になる穀物 |
| 五畜(ごちく) | 鶏 | 羊 | 牛 | 馬 | 豚 | 五臓の栄養になる家畜 |
| 五菜(ごさい) | 韮 (にら) |
らっきょう | 葵 (あおい) |
葱 (ねぎ) |
まめの葉 | 五臓の栄養になる植物 |
| 五果(ごか) | 李 (すもも) |
杏 (あんず) |
棗 (なつめ) |
桃 | 栗 | 五臓の栄養になる果物 |
| 五労(ごろう) | 歩 | 視 | 坐 | 臥 | 立 | 五臓の担当する動作。過度の動作は五臓の負担 |
| 五変(ごへん) | 握 | 動悸 | しゃっくり | 咳 | 慄 | 五臓の病変により、病人の発する症状 |
| 五刻(ごこく) | 朝 | 昼 | 午後 | 夜 | 夜半 | 五臓が活発になりやすい時間帯 |
| 五目(ごもく) | 黒精 | 目頭・目尻 | まぶた | 白目 | 瞳孔 | 五臓の働きの状態が現れる目の部位 |
| 五病(ごびょう) | 筋炎 | 眼疲労 | 筋肉痛 | 皮膚病 | 関節痛 | 五臓の機能不全により現れる病変 |
痛みからの解放(私の応急処置方法)
身体の特定の部位に痛みを覚えたときは、先ず、活動中の場合は直ぐに活動を停める。それから痛みの発生している部位に意識を集中し、痛みは何処から発生しているかを出来るだけ正確に把握する。痛みの部位が分かったら、心を落ち着け、身体を寛がせて、その部位に軽く掌を当てる。此処で注意すべき事は力をいれてはならないということだ。痛みの発生している部位に静かに掌を翳す程度に当て、10分間ほどじっとしている。これで大抵の痛みは治まる。その後、痛みの発生した原因を考え、適切な対処をする。重症が予想される場合は病院に急行し、運動などに原因する筋肉痛などの場合は休養を摂る。
身体の特定の部位に痛みを覚えたときは、先ず、活動中の場合は直ぐに活動を停める。それから痛みの発生している部位に意識を集中し、痛みは何処から発生しているかを出来るだけ正確に把握する。痛みの部位が分かったら、心を落ち着け、身体を寛がせて、その部位に軽く掌を当てる。此処で注意すべき事は力をいれてはならないということだ。痛みの発生している部位に静かに掌を翳す程度に当て、10分間ほどじっとしている。これで大抵の痛みは治まる。その後、痛みの発生した原因を考え、適切な対処をする。重症が予想される場合は病院に急行し、運動などに原因する筋肉痛などの場合は休養を摂る。
風邪を引かないために(私の対処方法)
風邪の予防のために留意していることは、
1.外出後の手洗いうがいは言うに及ばず
2.腹部と腰部を冷やさないこと。そのために冬期は腹部(臍の上)に下着の上から保温具を当てている。
3.身体を外気温の急激な変化に晒さないようにする。寒いところから急に暖かいところ、また、その逆の移動を回避する。
4.喉の痛みを覚えたときは、センブリ液を4,5滴喉に吹き付ける。プロポリス液が有れば喉の痛む部位に吹き付ける。
5.夜更かししない。特に疲れているときは、出来るだけ早く床に着く。
6.身体を濡れたままにしない。入浴後は髪などをよく乾かす。手洗い後は手をよく拭う。
風邪の予防のために留意していることは、
1.外出後の手洗いうがいは言うに及ばず
2.腹部と腰部を冷やさないこと。そのために冬期は腹部(臍の上)に下着の上から保温具を当てている。
3.身体を外気温の急激な変化に晒さないようにする。寒いところから急に暖かいところ、また、その逆の移動を回避する。
4.喉の痛みを覚えたときは、センブリ液を4,5滴喉に吹き付ける。プロポリス液が有れば喉の痛む部位に吹き付ける。
5.夜更かししない。特に疲れているときは、出来るだけ早く床に着く。
6.身体を濡れたままにしない。入浴後は髪などをよく乾かす。手洗い後は手をよく拭う。
若返りのために(私の心がけ)
1.身体を動かす。昼間は、じっとしている時間を出来るだけ少なくする。(ウオーキング、おはよう健康体操、プール)
2.一日に数度、深呼吸をする。(常に呼吸が浅くならないように注意する)
3.姿勢を意識し、猫背にならないように注意する。
4.「生きていることは素晴らしいことだ」という意識で生きる。(感謝の気持ちで人生を最大限に謳歌する)
5.常に何かに挑戦している。(極力古い考え、古い物を棄て、新しい気持ちで生きる)
6.新しい創造に挑戦し自分がこの世界を創っているという感覚を育む。
7.取り組んでいることは、意識がそれに向いている限り維持継続する。(逆境というものは無いが、忍耐が必要)
8.自分の肉体を、自分から見て出来るだけ若く見えるように整える。(何時も若くなっていることを意識している)
9.食べ過ぎ、飲み過ぎは厳禁。
10.あまり考えすぎない。(難問に当たったら直ぐに諦める。物事に執着しない)
11.若返りに有効なサプリメントを常用する。(プラセンタ、DHEA、OMEGA3、CoQ10、紅参)
1.身体を動かす。昼間は、じっとしている時間を出来るだけ少なくする。(ウオーキング、おはよう健康体操、プール)
2.一日に数度、深呼吸をする。(常に呼吸が浅くならないように注意する)
3.姿勢を意識し、猫背にならないように注意する。
4.「生きていることは素晴らしいことだ」という意識で生きる。(感謝の気持ちで人生を最大限に謳歌する)
5.常に何かに挑戦している。(極力古い考え、古い物を棄て、新しい気持ちで生きる)
6.新しい創造に挑戦し自分がこの世界を創っているという感覚を育む。
7.取り組んでいることは、意識がそれに向いている限り維持継続する。(逆境というものは無いが、忍耐が必要)
8.自分の肉体を、自分から見て出来るだけ若く見えるように整える。(何時も若くなっていることを意識している)
9.食べ過ぎ、飲み過ぎは厳禁。
10.あまり考えすぎない。(難問に当たったら直ぐに諦める。物事に執着しない)
11.若返りに有効なサプリメントを常用する。(プラセンタ、DHEA、OMEGA3、CoQ10、紅参)
| | ホーム | 小説「写像」 | 思考遊戯 | 参考資料 | 健康と長寿 | ギャラリー|コンタクト | |